『天平の甍』 井上靖 【あらすじ・感想】
初稿:
更新:
- 11 min read -
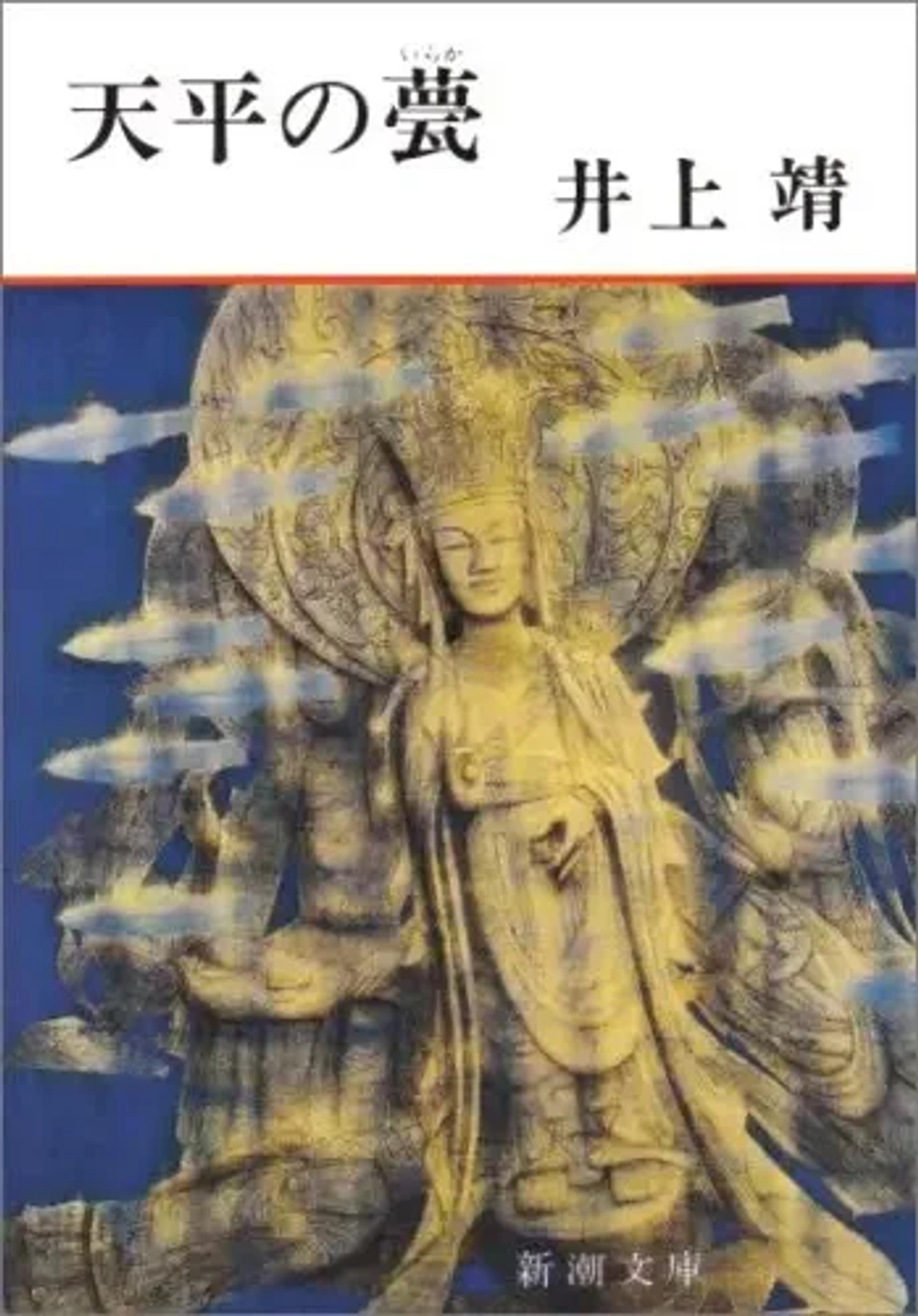
「天平の甍」のあらすじ
時は奈良時代・天平の世。近代国家成立を急ぐ朝廷は、先進国「唐」から多くを吸収するため、総員五百八十余名の第九次「遣唐使」を派遣する。
そこには留学僧として渡唐し、二十年の年月を経て高僧「鑑真」を日本へと連れ帰る男がいた。航海技術が未熟な時代に海を渡り、異国の地で生きた僧たちを丹念に描く歴史小説。
読書感想
読むキッカケ
あまり歴史小説のたぐいを読む機会がないのだが、某書評サイトでお薦めいただき「天平の甍(てんぴょうのいらか)」を読んでみた。
中国大陸の帝国が唐にかわっても、かつての遣隋使(けんずいし)と同様に、日本から中国の唐に、外交の使者の 遣唐使(けんとうし) を送ります。 — 中学校社会 歴史/奈良時代 - Wikibooksより引用
この史実の向こう側には多くの人が存在し、そしてそれぞれの人生があった。あたり前のことだが、そのことをまざまざと見せつけてくれる。
乏しい歴史知識しか持たないまま読み始めた歴史小説だが、丁寧に説明があり、何よりも読み手を強く惹きつける魅力に溢れる作品であった。
国家一大プロジェクトである「遣唐使派遣」には、まだ未成熟な国内仏教を発展させるため「唐」から高僧を招く目的があ。それを果たすには、現地で修行し、言葉を覚え、関係を作るための人材が必要である。
そこで選ばれたのが四名の若い僧侶たち。この四名と前遣唐使として先行して現地にいた一名を含む五名が物語の主要メンバーである。
この五名はそれぞれ個性的で、彼らの生き様が本作の一番の魅力であった。彼らの紹介と交えながら感想を記したい。
個性あふれる登場人物たち
アイ・アム・ヒーロー ~普照(ふしょう)
本作の主人公として彼を中心に物語が進んでいく。
当初は使命よりも自分が学ぶことに傾倒し唐を離れることに未練を抱くのだが、最後には留学僧で唯一生き残り、「鑑真」を日本へと連れ帰る。
人の気持ちの奥底を慮る優しさを持ち、広くものごとを受け入れる素晴らしき僧へと成長を遂げ事を成した、まさに「ヒーロー」。
お国のために尽くします ~栄叡(ようえい)
早い段階から、「膨大な経巻と鑑真を日本へ連れて行くことこそ我が使命」と宣言し、この「栄叡こそが遣唐使」と言っても過言ではない。
というか、他のメンバーは結構自分大好きで色々と驚かされる。 戒融とは仲が悪い。
終盤、志半ばで命を落とすシーンは本当に胸を突いた。 君の想い、忘れない。
オレもうやる気なくした カタカタカタカタ…ターン! ~玄朗(げんろう)
渡唐の時点から弱音全開、のちに日本へ帰る話が具体的になると
故国への思慕と、渡航に対する不安とに交互に襲われていた。彼はひどく怠惰になっていた。 — 本書より引用
この有様である。
一度目の帰国が頓挫すると「帰りたいけどお前らの冒険に付き合う筋合いはねーんだ」と言って姿を消す。
本当にこの人は何しに唐へ来たことやら。
幾度の失敗を経ていよいよ普照たちが鑑真を連れ日本に渡る話を聞きつけると、久しぶりに普照の前に姿を現し、「実はオレ、結婚して子どももいるんだ。仏門とかぜーんぶ忘れちゃったけど三人とも日本に連れってくれよ」と頼みこむ。
普照は全力で手配するが、帰国当日にバックれて「やっぱオレやめるわ」と手紙を送り付けてくる。
早すぎた個人主義、もうどこまでも「フリーダム」である。
こんなどうしようもない人物だが、厳しい時代にとても人間的で心のままに生きる彼は、私の中で「影の主人公」となったのである。
旅は道連れ世は情け ~戒融(かいゆう)
この人物も玄朗に負けない我がままっぷりを発揮し、「旅がオレを強くする」と言わんばかりに托鉢を頼りに旅立っていく。
ただ玄朗とは異なり、早くに言語を克服し、信念を持って旅だった彼は「哀愁ただよう孤独な旅人」である。 物語の終盤において、彼は絶妙な登場を見せる。
栄叡とは何かと折り合いが悪かったが、彼の死を知った時に見せた姿はグッとくるものがあった。 最後の数行でサラッと書かれた戒融のその後は「!?」となるが、味わい深い人物である。
私が死んでも代わりはいるもの ~業行(ぎょうこう)
私の写したあの経典は日本の土を踏むと、自分で歩き出しますよ。私を棄ててどんどん方々へ歩いていきますよ。多勢の僧侶があれを読み、あれを写し、あれを学ぶ。 — 本書より引用
上の四名の前に唐へ渡った先輩僧侶。
自分が修行するよりも経巻を写経することに一生を捧げた。
経巻に対する熱意は時に狂気を帯び、「日本への航海で荷物を捨てなければならないようなことがあれば私が海に入ります」と、普照に言わしめるほどである。
貸した本が汚れるとすごい怒る友人を思い出したが、重要な役割を果たす人物である。
読み応えのある大河小説
本作を読んでいるあいだ、彼らの個性的な人生の息吹きを感じ続けることができた。 細やかに、丁寧に、個性的な彼らを浮かび上がらせる著者の筆力に圧倒されっぱなしであった。
著者や司馬遼太郎のような歴史小説を書く人たちは、百年、千年たとうがいつの時代も私たちと同じ人間がそこに存在し、それぞれに異なる人生があることを本能的に解っているように思う。
ひとつ気になったのは、何度も日本への航海が失敗に終わり、年老いて視力を失うに至った鑑真が、なぜそうまでして日本へ行こうと思ったのかである。
デジタル大辞泉 - 鑑真の用語解説 - [688~763]奈良時代の渡来僧。日本の律宗の祖。中国揚州(江蘇省)の人。渡日を志して五度失敗し、その間に失明したが、天平勝宝5年(753)来日。東大寺に初めて戒壇を設け、聖武上皇らの帰依を受け、唐招提寺とうしょうだいじを創建して戒...
鋭い人は読み取ることができるのかもしれないが、私にはわからずじまい。
何かの機会に調べてみたい。
映像化について
また天平の甍は1980年に映画化されている。ぜひ一度見てみたいと思うのだが、DVD化されていないため、見るためにはビデオデッキが必要でありどうしたものか悩んでいる。
天平の甍の作品情報。上映スケジュール、映画レビュー、予告動画。天平年間、日本仏教界の確立のために黄土に渡った四人の日本人青年僧の青春と、唐の高僧、鑒真和上の二十年の歳月をかけて...
著者について
井上/靖 1907‐1991。旭川市生れ。京都大学文学部哲学科卒業後、毎日新聞社に入社。戦後になって多くの小説を手がけ、1949(昭和24)「闘牛」で芥川 賞を受賞。‘51年に退社して以降は、次々と名作を産み出す。「天平の甍」での芸術選奨(‘57年)、「おろしや国酔夢譚」での日本文学大賞(‘69 年)、「孔子」での野間文芸賞(‘89年)など受賞作多数。‘76年文化勲章を受章した。 — Amazon より引用