『同志少女よ、敵を撃て』(著:逢坂冬馬)のあらすじと読書感想
初稿:
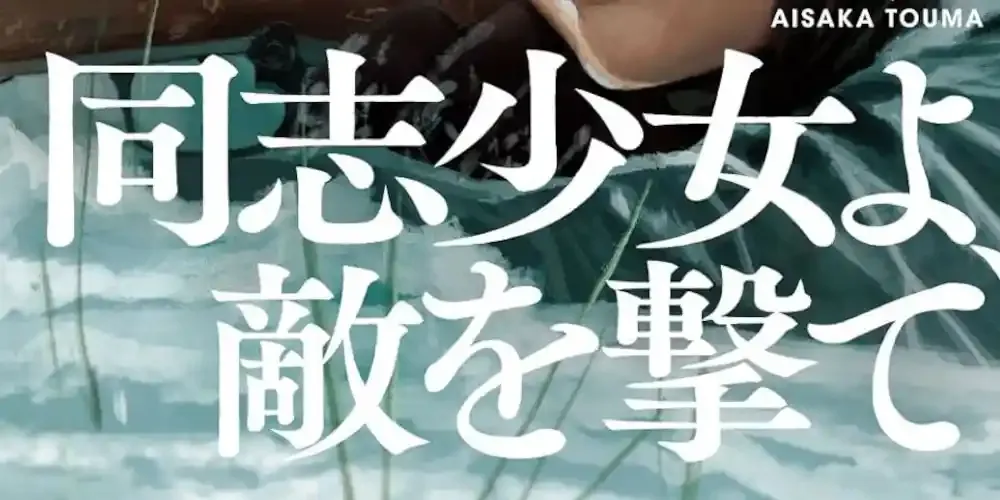
画像: 本書カバーより
あらすじ
独ソ戦が激化する1942年、モスクワ近郊の農村に暮らす少女セラフィマの日常は、突如として奪われた。急襲したドイツ軍によって、母親のエカチェリーナほか村人たちが惨殺されたのだ。自らも射殺される寸前、セラフィマは赤軍の女性兵士イリーナに救われる。「戦いたいか、死にたいか」――そう問われた彼女は、イリーナが教官を務める訓練学校で一流の狙撃兵になることを決意する。母を撃ったドイツ人狙撃手と、母の遺体を焼き払ったイリーナに復讐するために……。同じ境遇で家族を喪い、戦うことを選んだ女性狙撃兵たちとともに訓練を重ねたセラフィマは、やがて独ソ戦の決定的な転換点となるスターリングラードの前線へと向かう。おびただしい死の果てに、彼女が目にした“真の敵”とは? — 早川書房オフィシャルサイトより引用
読書感想
これまでいくつか戦時を舞台にした小説を読んできたが、本作はその中でも「女性兵士による視点で戦場を描く」という点で非常に新鮮だった。戦場とは、より過酷でより壮絶である事実を知らしめる作品、という意味の「新鮮さ」だ。
見どころの多い作品でもある。主人公セラフィマの成長譚、女性兵士たちの友情や絆、そして戦争の非情さと残酷さを描く点など、様々な要素が絡み合っている。作戦が展開する場面や狙撃手同士の対決など、次々に緊張感のあるシーンが展開され、エンタメ性も高い。
だが読後に最も強く残ったのは、細部で語られる登場人物たちの葛藤や苦悩である。本作が描き出す兵士、上官、戦場となった地で暮らす人々の誰もが壊れていた。
主人公セラフィマと同郷のミハイルは、戦争が持つ性質として「人間を悪魔にする性質」と表現していた。
戦場にも国際法や厳しい軍規などのルールが存在する。理性によって作られたルールを順守するには理性を駆動しなければならない。だが戦争はその理性を破壊する。理性を破壊された人間はミハイルの言う「悪魔」となってしまうのだろう。
心理的距離を置いて読み進めている間は「物語」であったが、一歩踏み込んで一人一人の心情に寄り添ってみると、彼ら彼女らの心情がいくつもの問いを投げかけてくる。
本作は、その後も描いている。
仮に生存し悪魔から人間に戻ることができたとしても、自らが行った加害と受けた被害によって、一生涯を苦しみながら生き続けることになる。
セラフィマの戦友の一人、ヤーナの壮絶な戦後はその事実を生々しく表現していた。ヤーナの描写を読みながら、彼女と同様、PTSDに苦しむ元狙撃手を描いた『アメリカン・スナイパー』という映画を思い出した。
戦中から戦後も続くこの地獄のような状況は人工的なものである。自然災害や疫病などの天災とは異なり、人間が引き起こしたものである。とりわけ近代の国家間戦争においては為政者だ。
「戦うか、死ぬか」
セラフィマを狙撃手に導いたイリーナが、セラフィマへ最初に投げかけた問い。これは彼女の言葉であると同時に、戦争がすべての人に突きつける現実でもある。
この残酷な2択を強いる状況、つまり戦争の開始を決定する者たちを、私は決して許すことができない。読後、真っ先に思ったことだ。
と同時に、フィクション上の人物ではあるが、セラフィマやイリーナ、戦争で傷ついたすべての人々の精神が少しでも安らかであることを願わずにはいられない。
著者について
逢坂冬馬 (あいさか・とうま) 1985年、埼玉県生まれ。明治学院大学国際学部国際学科卒。2021年、『同志少女よ、敵を撃て』で第11回アガサ・クリスティー賞を受賞してデビュー。同書は2022年本屋大賞、第9回高校生直木賞を受賞、第166回直木賞候補となった。2023年には第2長篇『歌われなかった海賊へ』を刊行、第15回山田風太郎賞の候補となった。2025年には第3長篇『ブレイクショットの軌跡』を刊行、第38回山本周五郎賞候補、第173回直木賞候補となった。 — 『早川書房 逢坂冬馬の本』特設サイトより引用
戦争(暴力)ついて思うこと
以下は個人的思考の備忘録であり、余談である。
戦争・紛争、いじめやDV、虐待、テロリズムなど、影響範囲の大小はあれど共通するのは「暴力」である。
これらを主題とした情報を見聞きするとき、概ね「いかに暴力を減らすか」「いかに暴力を防ぐか」という文脈で語られることが多い。
そのたびに、私は「暴力をなくすことはできるのか?」と自問する。
今回読んだ『同志少女よ、敵を撃て』においても、暴力について幾度も考えさせられた。本書の感想と直接関係するわけではないが、湧いてきた思考を備忘録としてメモしておきたい。
暴力とは何か
私は、「暴力は人間のみならず生命の本質」であると考えている。
仮に暴力を、「自身の利益を確保、ないし最大化する行為」として捉えた場合、そのような営みは自然界ではもちろんのこと、私たちの体内でも細胞レベルで常に繰り返されている。
そのような思考は『われわれはなぜ死ぬのか』という作品を読んだ際に強く意識するようになった。
私たちは、生れ、成長したあと、老いて死んでゆくものだと思っている。けれどDNAは受精の瞬間から、死に向けて時を刻み始めている。産声を上げる10ヶ月も前から、私たちは死に始めているのだ。生命が36億年の時をへて築きあげたこの巧妙な死の機構とはどのようなものなのだろうか?
暴力をなくすことは可能か
暴力の否定、廃絶の議論を目の当たりにしたとき、それは「生命の本質を否定することは可能か?」という問いとして私は受け止めてしまう。結果として、暴力をなくすことは不可能である、という結論に至る。(すべての生命を死滅させることができれば別だが。)
仮に暴力を止めることは不可能と定義した場合、では「戦争をなくすことは可能か?」という問いに対しては、別の答えがあると考えている。
戦争の目的が、領土や資源などの獲得、政治的な支配などである場合、「権力を持つ者または団体の欲望を制御することは可能か?」という問いに置き換えることができると思う。だが国際連盟、国際連動、国際刑事裁判所など、国際社会における暴力の制御を目的とした組織やルールによる試みは成功しておらず、不可能ではないが非常に困難であることの現れであろう。
一方、今のイスラエルやホロコースト、あるいは宗教的な狂信に基づく場合など、戦争の目的が「特定の集団を抹殺すること」である場合はどうだろうか?と考える。
思想や信念に突き動かされる衝動は、理性ではなくまた本能でもない別の何かであるように感じる。何であるかが掴めていない以上、答えを想像することもできない。
このあたりに言及した本を読んでみたいといま思った。
つまり、暴力をなくすことはできないが、暴力につながる動機にフォーカスすることで、抑制ないし対処することは可能かもしれない、と微かな希望を持っている。
いじめやDV、虐待なども同様に、我々は本質的に暴力を抱えた生命体であることを受け入れた上で、強いストレスや孤立や依存症など、暴力を引き起こす状況を意識するよう心掛けている。
自分ができることは何か
前述のとおり、暴力は人間の本質であると私は考えている。
かつて私たちの遠い祖先は自然界の生物と同様、暴力は自然な行為の一つとして行っていたのだろうと想像する。
だが、いつかの誰かが「暴力を止めよう」と、考えたまではいかずとも、感じた人がいたのではないかと想像する。
人間が理性を獲得する以前に、暴力を嫌悪する感情が芽生えたのではないかと想像する。
それは、自然に抗うものである。自然に抗うことは、自然の摂理に反することでもある。
にもかかわらず、それは今日まで受け継がれ、非常にゆっくりではあるが、確実に広がっていると私は信じている。
暴力は人間の本質と考えると同時に、最初に暴力を否定した誰かを思いながら、私もそれを受け継いだ人たちの列に加わりたいと強く思う。
歴史は思いの総数によってのみ動くと信じている。