『論理的思考と文化的基盤』 渡邉雅子 【読書感想】
初稿:
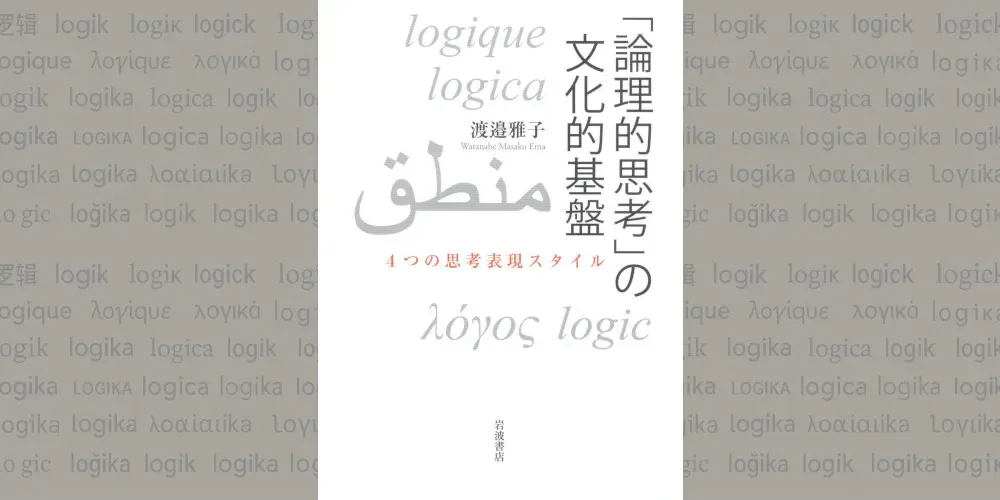
『論理的思考と文化的基盤』の概要
普遍的であるはずの「論理」と「合理性」。それは文化によって大きく異なり「価値観」とつながる。「文化の多様性」という言葉に逃げ込まず、それぞれ4つの原理を代表する日本・アメリカ・フランス・イランの思考表現スタイルから4タイプの論理と合理性を明らかにする。ポスト近代を生き抜く知恵となる比較文化論の集大成。 — 岩波書店 より引用
読書感想
『論理的思考と文化的基盤』の構成について
本書は序章からはじまり、第1部から第3部までの構成で展開される。
序章では本書の構成と目的を示し、第1部では教育文化のモデルと思考表現スタイルについて解説する。第2部では四ヵ国の教育原理モデルと思考表現スタイルを詳細に分析し、第3部で各国の違いを比較・考察する。第3部に含まれる終章では、本書を通じて得られた知見をもとに、現代社会を生き抜くための提言がなされる。
では、実際に各章の内容と読後の感想を述べていきたい。
序章 ~ 第1部 教育文化のモデルの構築
「ロジカルシンキングが重要だ」「結論から延べよ」等々。社会に出ると、特にビジネスの場面でこうした言葉をよく耳にする。
ロジカルシンキング=論理的思考の「論理」は、世界共通の普遍的なものと思っていた。結論を最初に示すスタイルは、最も合理的で優れた手法であるから多用されているものと信じて疑わなかった。
本書『論理的思考と文化的基盤』は、私の認識を根底から覆す。
タイトルにある「論理的思考」と「文化的基盤」は、おおよそ結びつかない概念に思える。しかし著者は、論理的思考のスタイルが文化的基盤に深く根ざしていることを、四ヵ国(アメリカ、フランス、イラン、日本)の「作文」と「歴史教育」を比較・分析することで明らかにしている。
そして、違いを示すにとどまらず、それぞれを選択・活用することの重要性を提言する。
近代で普遍と捉えられていた論理と合理性を問い直し、「いかに論理的に描き、語るか」、「合理的に行動するか」という議論から、いかなる「思考表現のスタイルを学んでいるのか」、その背後にある論理性と合理性を支える原理は何か、そしてどれを「選び取るのか」という議論へと視点を移す。本書がその議論の端緒を開く一助となることを願う。 — P12 序章より引用
常識をひっくり返された上に、さらなる提言に戸惑うかもしれない。
だが、本書を通じて得られる知見は、現代社会を生き抜く上で非常に有用であり、豊かな人生を歩むための重要なヒントが詰まっている。
教育原理と思考表現スタイル
学生時代を通じて形成された思考や価値観は、社会に出るとまったく通用しない。そんな経験を多くの人が持っているのではないか。
この現象は、日本の教育と社会の場では、まったく異なる論理的思考スタイルが駆動することに起因する。本書を通じ、そのことをよく理解することができる。
著者は「アメリカ」「フランス」「イラン」「日本」の教育原理を、「経済原理」「政治原理」「法技術原理」「社会原理」の4つに分類し、それぞれに根ざした表現法を「思考表現スタイル」と名付ける。
本書では、それぞれの社会・文化に根差した思考とその表現法を「思考表現スタイル」と名付ける。思考表現スタイルとは、「書く型」に現れる「考える道筋」、「考える手続き」を指す。つまり書く型に現れる「思考の型」である。 — P51 第一部 教育文化のモデルの構築 より引用
そして、思考表現スタイルの違いを生み出す要因として、各国の「作文教育」と「歴史教育」に着目する。
小論文の型を、思考を表現する「スタイル(様式)」と捉えることで、どちらがより「論理的なのか」の序列ではなく、小論文の型に現れる論理とはどのようなものか、それぞれの思考に独特の癖とは何かが「様式の違い」として特定できる。さらに、歴史教育の「過去の語り」における過去の出来事の解釈の方法とそれを反映させた未来の予想の方法からは、「物事はどのように起こるのか」という日常の推論の型が特定できる。 — P51 第一部 教育文化のモデルの構築 より引用
作文?歴史教育?と正直思った。学生時代を思い返してみても、それほど強い印象は残っていない。
しかし、著者の分析を読み進めるうちに、確かに自分の思考スタイルが日本の教育原理に深く根ざしていることを実感する。
なぜ学生時代と社会人になってからギャップに苦しむのか、日本とアメリカのビジネス文化がなぜこれほどまでに異なるのか、そうした疑問に対する答えがこの後に続く分析で明らかになる。
第二部 四つの教育原理と四カ国の思考表現スタイル
第二部では、各国の教育原理モデルと思考表現スタイルの詳細が示される。
各教育原理モデルごとに感想を記す。
アメリカ:経済原理モデル
冒頭で述べた「結論から述べよ」は、アメリカ式エッセイの典型であり、「五パラグラフ・エッセイ」と呼ばれる。
主張と三つの根拠と結論から構成されるアメリカ式のエッセイは、五つのパラグラフ(段落)から構成されることから五パラグラフ・エッセイとも呼ばれている。 — 本書 P59 より引用
私が知るビジネスの現場では、メール、プレゼン、報告書など、あらゆる場面でこのスタイルが求められた。
その理由は、五パラグラフ・エッセイが最も合理的かつ効率的であるから、と思い込んでいたが、興味深い経緯があった。
アメリカは他国に先駆けて高等教育の大衆化が進んでいたが、ベトナム戦争から帰還した若者が復員兵援護法(GI Bill)によって大学に殺到して高等教育の大衆化が加速すると、多様な学力レベルや文化的背景を持つ学生にいかに学術的な論文を書かせるかが大きな問題となった。その苦肉の策として、言語学者のクリステンセンら(F. Christensen and B. Christensen)によって推奨されたのが、主張を最初に持ってきて演繹的に論を進める形式だった。 — 本書 P62 より引用
なんと、教授側の都合で生まれたスタイルだというではないか。しかも割と最近の話で、ビジネスに最適化されたのは後天的な理由によるものだ。
とはいえ、アメリカの思考表現スタイルは、合理性を追求した経済原理に適っているのだろう。
アメリカの作文教育は、相手を説得し、行動を促すことを目的としている。また、歴史教育においても、歴史を動かす主体は「目的を持つ人間」であり、歴史的事象はその人間が積み重ねた判断の行動の結果として説明される。
リベラル民主主義の名のもとに、経済領域の原理を支える技術と価値観が、エッセイによる論理的思考と、歴史教育における時間と因果律をもとにした行為の合理化の方法を通してアメリカの思考表現スタイルを形成している。 — 本書 P97 より引用
アメリカの映画やドラマで、「アメリカだなあ」と個人的に感じることがよくある。その背景にある思考表現スタイルは、教育の段階で徹底して培われたものであると分かった。この感覚は、私にとって非常に重要であり、好き嫌いの感情を超えて「理解した」と思えるものだった。
フランス:政治原理モデル
欧米、西側諸国など、アメリカとヨーロッパを同一視する傾向が存在する。しかし、フランスの思考表現スタイルはアメリカとは大きく異なる。異なるどころか、真逆であると言っても過言ではない。
個人的に、もっとも興味を惹かれたのがフランスの政治原理モデルである。
宗教支配を脱し、フランス革命を経て以後、その後も王政復古や帝政を経験の果てに成立した共和制は、フランスの思考表現スタイルに大きな影響を与えている。
フランスは革命後も王政復古や二度の帝政を含め四度憲法が書き直され十五の政体が現れるという変化を体験し、この政治的混乱による血みどろの歴史を二度と繰り返さないために、極端に触れず熟考して判断できる政治的主体の育成を行う教育の象徴としてディセルタシオンは創られた。 — 本書 P101 より引用
アメリカの五パラグラフ・エッセイに対し、フランスの論文形式は「ディセルタシオン(Dissertation)」と呼ばれる。
最初に結論を示し、それを相手に受け入れさせる目的で論を展開する五パラグラフ・エッセイとは異なり、ディセルタシオンは弁証法的に論を進める。
ディセルタシオンにおいては、〈正〉と〈反〉二つの視点間の「矛盾の解決」を行うことが目的であり、それが論文構成の原理となっている。しかしこの矛盾は与えられた問いに常に明示されているわけではなく、書き手が鍵になる概念を導入部分で定義することによって積極的に反論を見つけ、矛盾を作り出さなければならない。 — 本書 P103 より引用
〈正〉と〈反〉についても、対立する両極として捉えるのではなく、「その間のグラデーションであらゆる可能性を吟味していく」目的があるという。
そして、〈正〉と〈反〉を展開した後、最終的に導き出される結論〈合〉は単なる折衷案や妥協点ではなく、私たちが紡ぐ歴史のひとつの「過程」として捉えるという。
〈合〉の結果がさらなる「問題提起」を生んでいくので、「問題解決」や「正解」という考えにはなじまないのである。先人の答えも、自己の答えも常に問い直しつつ、それを最終的なものでなく歴史の中に位置づけられたひとつの「過程」と捉えるのである。 — 本書 P110 より引用
キリスト教圏は二元論的思考が当たり前と思い込んでいたが、ディセルタシオンに見られる弁証法的思考に、共和制を追求するフランスの確固たる意志を感じる。
ちなみに、小論文に弁証法形式を用いる国がヨーロッパには多いようだ。フランスの特徴としては、論を展開するにあたり、個人の体験や感情を排除し、厳密な引用を用いる点が挙げられるそうだ。理由として、まだ経験が浅い学生たちに2000年を超える蓄積された知識をメニューとして提供し、多様な視点からものを見、思考する力を養うためであるという。
日本で教育を受け暮らしている私にとって、とても共感を覚える内容だった。できればゼロ歳児からフランス式教育を受けてみたかったと思うほど。
一方で、現在のマクロン大統領の独断や強引な振る舞いから、ディセルタシオンに込められた理念は感じられず、教育は必ずしも社会に反映されるわけではないことも併せて認識しておく必要があるだろう。
イラン:法技術原理モデル
ペルシャ帝国の歴史を持ち、イスラム革命を経て成立した。これ以上の知識を持たない私にとって、イランの法技術原理モデルは未知の領域。
「神」という絶対的な存在が法の根源にあることが、イランの思考表現スタイルに大きな影響を与えている。自由な社会で暮らす人間からすると、一見、理解しがたい窮屈な印象を受ける。
だが、自由な社会の副作用として生じる混沌や不安定さを考えると、社会に絶対的な定理を設けることの合理性や安心感を理解できる気がする。
イスラームの教義においては、神の意志が具現された諸法は不変であり世界のすべての存在において定立しているとされる。その諸法は原因と結果の関係によって説明され、個人が真と偽、善と悪のいずれか一方を選ぶと、その選択の結果は明確に知らされることになる。選択は自由意志によって行われるとされていても、原因と結果は個人の外側に規範として存在し、従うべき道は示されている。 — 本書 P174 より引用
イランの作文教育は、「エンシャー(ensha)」と呼ばれる。
ペルシア語で「エンシャー(ensha)」とは「作文、創作、あらゆる種類の文学的な書物、書く教育、書物一般、雄弁かつ能弁な文章一般」を意味しており、学校においては作文と作文教育を指す。 — 本書 P142 より引用
五パラグラフ・エッセイやディセルタシオンのように論を展開し結論を導くものとは異なる。なぜならこの国では、絶対的な神の法がすでに存在しているからだ。結論は神がすべて示しているため、おのずと作文の目的も変わってくる。
現代の多くの国で重視されている「論証すること」は、イランの作文には馴染まない。実際、論証型の意見文や小論文の形式はイランの作文教科書には含まれていない。論証は、書き手の主義の正しさを経験的なデータで示したり、引用によって書き手の解釈やものの見方の正しさを証明したりする。しかし長い時間をかけて練り上げられ広く共有されたことわざが意味することや、この世の経験を昇華させる機能を持つ詩の一節、そして神の為したこの世界の事柄を論証してみせることには無理があると同時に意味がないからである。 — 本書 P180 より引用
エンシャーでは、最後に詩やことわざを引用し、神の法に照らし合わせて結論を導く。個人の意思や理性が重んじられる社会と異なり、長い時間をかけて積み重ねられてきたイランの歴史や宗教的伝統に基づく価値観が重視される。
目的は異なるが、考え方としてはフランスのディセルタシオンに近いものを感じる一方、アメリカとは対極的であることが分かる。
日本:社会原理モデル
自分が受けてきた教育内容を分析したことはなかった。本書が示すその内容は、ある意味で衝撃的であり、かつ非常に納得できるものだった。
先の大戦で敗戦を経験し、アメリカの占領を受けたにもかかわらず、日本の教育原理モデルは社会原理に根ざしている。ベトナム戦争後に誕生した五パラグラフ・エッセイはまだ存在しなかったこの時代に、日本は明治時代から続く「綴方(つづりかた)」教育を確立していた。
アメリカの新教育由来の教育法(プロジェクトメソッドなど)は、今日の日本の教育に引き継がれているが、日本の思考表現スタイルに伝統的な価値観と思考法をそれと意識することなく残すことができた要因のひとつには、綴方の伝統と実践の貢献があった。 — 本書 P193 より引用
綴方は、子どもの見方・考え方を尊重し、自己表現を促す教育法である。
義務教育でよく課された読書感想文では、同じ気持ちになってみることを求められた記憶がある。実は、この教育方法は制度化されたもので、指導例でも紹介されている。
しかし社会原理を体現する日本に特徴的な点は、主人公の置かれた場に自分も身を置いて(主人公になりきって)共感する方法が定式化され、制度化までされている点である。さらに上記の指導例の「白馬やスーホになって」という言葉に現れたように、同じ方法を人間のみならず動物にも適用することである。国語の教科書や作文の指導書には、魚、植物、そして無生物の物にすら「なりきって」感じ、考え、書くことが勧められている。 — 本書 P200 より引用
さらに衝撃を受けたのは、感情移入だけでなく、共通認識を形成するための刷り込みも行われている点だ。
感想文は、主観的な感情や考えを記しているように見えながら、実際には学級の話し合いによって調整された社会的な読みを我がものとして書いたり、友だちとの相互評価によって考えを変えたり視点を変えたりする価値観のすり合わせが行われており、そこには「他者の視点から自己の考えを見直す」教育的な価値観が体現されている。 — 本書 P203 より引用
話し合いで得られた共通認識を、自らが至った結論であると子供たちは思い込む。これにより、個人の意見を尊重しつつも、集団としての同質性を保つことができる。
このような光景は、確かに覚えがある。世間体、同調圧力、空気を読むといった言葉で表される、日本社会の特徴的な価値観は、教育の段階で培われていることがよく理解できた。
明治以降に確立された教育であるがゆえに、統治の意図を感じなくもないが、それだけでもないように思う。
戦後、長きにわたり戦争が無かったにもかかわらず、毎年のように財産やコミュニティーが強制的にリセットされる地震や台風といった災害が各地で発生するこの国において、社会原理モデルが培われてきたのは、必然的な帰結であったと見る方が自然に思える。
歴史教育においても、独自性を感じる部分があった。
持続可能な社会とは、換言すれば変化しない社会、すなわち自然と共存し、自然の収奪による経済成長を目指さない社会である。高校の歴史総合では、科学技術の正負の二面性を歴史から考えさせることで、科学主義と結びついた資本主義と軍需産業、その背後にある国家主義、イデオロギーといった近代批判の目を養うことで、「より良い国」、「持続可能な社会」という価値目標を一貫性のあるものとして具体化させていく。 — 本書 P222 より引用
歴史認識で揉めている話題をときどき耳にするが、そんなことより、持続可能な社会を目指すという大義名分のもとに、歴史教育が行われていることに驚いた。しかも、強めの新自由主義批判が含まれているとは。
日本はアメリカの影響を強く受けていると思い込んでいたが、フランスやイランに近く、アメリカから最も遠い教育原理モデルを持つのは驚きだ。
終章 教育文化の四元モデルから見る日本の立ち位置
ここまでで、詳しく示された各国の教育原理モデルを、終章では以下のようにまとめている。
経済原理では「効率性」、政治原理では「十分な審議」、法技術原理では「真偽の決定」、社会原理では「共感」が各原理の思考表現スタイルの主導的な観点となっている。教育目的として「技術」を掲げる経済原理と法技術原理においては、「結果重視」で決まった結論に向けて目的論的に議論を進める。それに対して、「価値」を目的として掲げる政治原理と社会原理は、議論の「過程を重視」してその過程からそれぞれの原理の価値観を学ぶ。 — 本書 P262 より引用
アメリカは優れていて、日本は何かと劣っているという思い込みが、正直少なからず私の中にあった。しかし、それは経済原理にもとづく一つの側面に過ぎないことが理解できたし、重視する価値観がそもそも異なっていることも分かった。異なる価値観が生まれる背景には、その国や地域の自然環境や歴史的経験が深く関わっており、どれが優れているとか劣っているとかいった単純な話ではない。
最後に著者は、「ポスト近代の日本の立ち位置」として、本書が示す四つの思考表現スタイルを活用することの重要性を説く。
日本に求められているのは、自分の立ち位置とその長所短所を自覚した上で、四つの原理の思考表現スタイルを書く・語るコミュニケーションの「スタイル」のレベルで使いこなせるようになることである。 ~(中略)~ そのためには、まず四つの思考表現スタイルがあるということを知ること、その背後の原理を理解することが重要である。私たちが選択できるのは、選択肢を思い描ける時のみだからである。 — 本書 P275 より引用
ここまで読み進めてきたら、著者の提言は非常に納得できる。
私たちは、ひとつの成功体験に紐づくスタイルに固執しがちだ。平気でその手法をあらゆる場面に持ち込もうとする。
周りを見渡してみると、仕事で身につけた論理を家庭や友人関係に持ち込み、摩擦を生んでいる人を少なからず見かける。ビジネスの場では経済原理モデルが有効であっても、家庭や友人関係では社会原理モデルが相応しかったりする、ということではないか。
議会はもちろん、会議や地域コミュニティー等々、政治的なプロセスが執り行われる場において、経済原理や社会原理を過度に持ち込むことが混乱の原因になることも分かってきた。多様な意見をゴールへ導く仕事をするには、それに相応しい思考表現スタイルを選択することが重要なのだ。
おわりに
私は短い言葉で結論だけを言い切るタイプの人間が苦手だ。よくよく聞いてみると論拠が希薄だったり、バイアスまみれの域を出ていない思いつき、といったケースがあまりに多い。だが、社会では短文言い切りが主流。その流れに素直に従えない私の性質は非常にやっかいであり、コンプレックスでもある。
本書は、そんな私の救いとなった。
私が抱える思考表現スタイルと、仕事等で直面する思考表現スタイルは、ただ単に異なるだけなのだ。この理解は、一気に視界が開ける感覚をもたらしてくれた。
文化によって論理は異なり、個人単位ではさらに多様であることの心づもりができていると、心理的な障壁は大きく下がることを実感している
本書に出会えた幸運と、35年の月日を費やして研究を続けてこられた著者に深く感謝したい。
著者について
渡邉雅子 名古屋大学大学院教育発達科学研究科教授. コロンビア大学大学院博士課程修了. Ph. D.(博士・社会学). 専門は知識社会学, 比較教育, 比較文化. 主著に『「論理的思考」の社会的構築――フランスの思考表現スタイルと言葉の教育』(岩波書店, 2021 年), 『論理的思考とは何か』(岩波新書, 2024 年), 『納得の構造――日米初等教育に見る思考表現のスタイル』(東洋館出版社, 2004 年). 編著『叙述のスタイルと歴史教育――教授法と教科書の国際比較』(三元社, 2003 年), “Typology of Abilities Tested in University Entrance Examinations: Comparisons of the United States, Japan, Iran, and France.” Comparative Sociology. 14(1). 2015. pp. 79-101 など. — 本書より引用